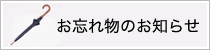インフォームドコンセントとShared decision making(SDM)(共同意思決定)の違い
アイさくらクリニックが開院した2001年は
インフォームドコンセントの概念を持って進めるのが推奨されていました。
私も出来るだけ実践してきました。
しかし今は新しい概念「Shared decision making(SDM)(共同意思決定)」が
重視されてきています。
SDMの始まりは1980年代から1990年代にかけて医療分野で発展した概念です。
この時期、医療における患者さん中心のアプローチが重視され始め、
患者さんの自己決定権やエンパワーメントが重要視されるようになりました。
SDMの概念は、医療者と患者さんの間の意思決定プロセスをより協働的で
対等なものにするために提唱されました。
具体的には、患者さんが治療や検査の選択肢について十分な情報を得た上で、
自らの価値観や希望を反映させた決定を行うことを目指しています。
インフォームドコンセントは、患者さんが治療や検査の前に、
その内容やリスク、代替案、予想される結果について十分な情報を提供され、
自らの意思で治療に同意するプロセスを指します。
医療者は患者さんに対し、わかりやすい言葉で必要な情報を提供し、
患者が理解し、納得した上で治療に同意することを求めます。
このプロセスは、患者の自己決定権を尊重し、
不必要な医療行為や患者に不利益をもたらす医療を避けるために重要です。
一方、Shared decision making(SDM)(共同意思決定)は、
インフォームドコンセントの一歩進んだ形として考えられます。
SDMでは、医療者と患者さんが対等な立場で協力しながら
意思決定を行います。
SDMの目的は、患者さんの価値観やライフスタイルを考慮し、
医療者が持つ専門的な知識と患者の希望を調和させて最適な
治療法を選択することです。
これには、医療者が複数の治療オプションを提示し、
各選択肢のメリットとデメリットを説明し、患者さんがどのような治療を望むかを共に考えるプロセスが含まれます。
当院でもよく、患者さんに『どちらを選びますか? どの様にしましょうか?』など
質問することがあります。
先日患者さんから『私は素人なので分かりません』との声が上がりましたが、
私からの一方的な医療の提供でなく患者さんに治療に参加して貰いたいと思い提案しているので、
治療によるメリット・デメリットを患者さんも自分のこととして
治療に参加して貰いたいと思っています。

インフォームドコンセントは、主に医療者から患者さんへの一方的な情報提供と
それに基づく同意を求めるのに対し、
SDMは、患者さんが医療決定に積極的に参加し、医療者と協力して治療方針を決定する
双方向的なプロセスです。
SDMでは、患者さんが自分の価値観や生活状況に基づいて最適な選択肢を
見つけることができるため、患者さんの満足度や治療への積極的な参加が
促進されるとされています。
これにより、患者さんは治療結果に対する納得感が高まり、
治療の質が向上することが期待されます。
まとめると、
インフォームドコンセントは患者さんの同意を得るための基本的なプロセスであり、
SDMはそのプロセスを発展させ、患者さんと医療者が共に意思決定を行う協働的なアプローチです。
どちらも患者さんの自己決定権を尊重する点で重要ですが、
SDMはより深い患者参加を目指しているインフォームドコンセントの進化形だと言えます。

当院ではShared decision making(SDM)(共同意思決定)を行うにあたり
MBC(メジャーメントベイスドケア)を活用しています。
治療の流れをグラフにして、治療の変わり目の時の判断材料にする。
例えば休職中の方へ本人と職場復帰の判断材料にしたり、
職場の産業医へMBCのグラフを印刷して復帰の許可をもらう材料にしたり、
病状悪化の時、薬物療法を単剤療法から併用療法、もしくは増強療法に移行するか?
治療が思ったように進んでないと感じる方へ長期的なグラフを振り返ってみたり
(少しは良くなってることが分かって安心されそのまま進めることも多々)
もしくは治療内容を変えるなど。
治療の満足度を高めるためこれまでも、これからも工夫を続けていきたいと思っています。


メニュー
ジャンル
〒 810-0001
福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)
TEL:092-738-8733